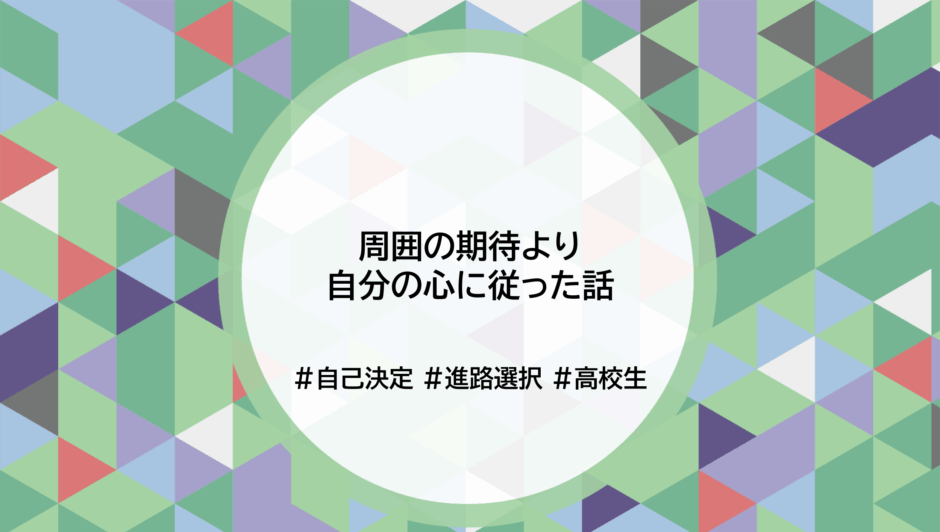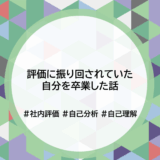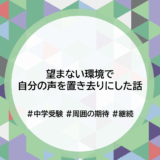今回は、エンジニアのウルフィさんに「当時困っていたこと」や「今みんなに伝えたいこと」を聞いてきました!
【背景】周囲の期待より「好き」を選んだ進路選択

ウルフィさんは高校時代、進路について、どのように考えていましたか?

私は理系科目が得意で、中学・高校とずっと理系のクラスに進んでいました。

「得意だから進んだ」というよりも、周囲の影響が大きかったです。

祖父母を含め、家族は理系出身で、その分野の職に就く人が多かったんです。

そのため、「自分も理系の道に進むんだろうな」と、自然に思い込んでいました。

まるで当たり前のことのように感じていたので、特に何も考えていませんでした。

「将来の自分」を意識し始めたのは、何がきっかけでしたか?

高校2年生のときに、ある映画を観て、ものすごく衝撃を受けたんです。

映画を通して、知らない世界にたくさん触れることができました。

また、映画は言語や文化、価値観の違いに出会わせてくれる存在でもありました。

映画の面白さに惹き込まれ、気づけば自分の世界が一気に広がった感覚があったんです。

そのときから「私は何が好きなんだろう?」「何がしたいんだろう?」と、はじめて自分の頭で考えるようになりました。

考えを重ねるうちに、進路のことにも少しずつ意識が向くようになっていきました。

ようやく、自分の頭で将来と真剣に向き合い始めた、という感じですね。

そして、高校3年生のときに、理系から文系の大学へ進路変更しました。
【困りごと】迷いながらも覚悟を重ねていった日々

理系のクラスにいながら、進路を変えることに迷いはありませんでしたか?

正直、迷いはありました。周囲の影響もあり、小さい頃から「私は薬剤師になるものなんだ」と思っていたんです。

振り返ると、家族の影響もあり「資格がある」という点に惹かれていたのだと思います。

特に、小さい頃から「女性は資格のある職業に就きなさい」と言われて育ちました。

理系のまま進み続けることは、周囲から見れば「現実的」で「安定した選択」だったかもしれません。

けれど、自分の「好き」を大切にしたいと思ったからこそ、文系の大学に進む道を選びました。

進路を決めた後、周囲との違いに不安はありませんでしたか?

家族やクラスの友人とは違う進路を選んだため、「本当にこれでいいのかな?」という不安は、ずっと心の中にありました。

「でも、私はこっちが好きだな」という想いもあって、少しずつ、気持ちに折り合いをつけていったように思います。

ウルフィさんは当時の選択をどのように感じていますか?

難しい選択でしたが、考えることをやめず、自分で決断できて本当によかったです。

違和感をおざなりにせず、自分で考え、自分自身で決め切ることができました。

あのまま理系に進んでいたら、きっと納得できないまま、どこか引っかかりを抱えて今も過ごしていたと思います。

その決断を貫けた原動力は、どこにあったのでしょうか?

特に映画を通して、さまざまな生き方があることを知れたことが、大きな原動力になりました。

世界には多様な価値観や選択肢があるのだと気づいたとき、「どのような人生を選ぶか?」が自分にも問われている気がしたんです。

だからこそ、「じゃあ私はどうする?」という問いに、真剣に向き合うことができました。
【合理的配慮】

当時のウルフィさんに声をかけるなら、何と伝えたいですか?

そうですね。「違和感はそのままにせず、考え抜いて決断してほしい」と伝えたいです。

自分の頭と心で考えて決めたことであれば、きっと、その選択は間違いではないからです。

そのためにも、決断を恐れず、選ぶ前にはしっかりと考えることが欠かせないと思っています。

当時、映画を通してだけでなく、家族や友人の声にも耳を傾けるようにしていました。

まずは、いろんな意見や価値観に触れ、自分の中にたくさんの材料をインプットします。

そうして得た材料をもとに「自分はどうしたいか?」と問いかけ、じっくり考えて決めることが何よりも大切です。

その考え方は、今のウルフィさんの生き方にもつながっていますか?

はい。今も変わらず大切な軸になっていますし、ずっと同じ姿勢で生きています。

文系の大学に進んだ後も、留学をしたり、新しい環境に飛び込んだりしながら、たくさんの選択を重ねてきました。

エンジニアの仕事をしていることも、その時々で「自分はどう生きたいか?」と考え、選んできた結果です。

私の人生を、私自身の選択と意思で進んでいくという感覚が、とても楽しいです。

当時、周囲の人たちに「こうして欲しかった」と思うことはありますか?

誰かに「こうして欲しかった」という気持ちよりも、「こうあるといいな」と思う社会の姿はあります。

それは、社会全体で「〜すべき」と一括りにするのではなく、もっと1人1人に多様な選択肢を選べる余地を与えることです。

断定や押しつけではなく、個人の意思や考えを大切にし、尊重することが当たり前の世の中になったら素敵ですね。

自分で考える力を育む教育や、それを支える社会が、もっと広がればいいなと思います。
- 同じ境遇の人へ
周囲と異なる選択に、不安や戸惑いを感じる瞬間もあるでしょう。
それでも、自分の気持ちに耳を傾けて悩んだ時間は、やがて「自分を信じて進む力」となり、そっと背中を押してくれるはずです。 - 身近な人(家族・親友・恋人)へ
誰かが悩んでいるとき、つい励ましたり、アドバイスしたくなることがあるかもしれません。
そのようなときこそ少し立ち止まり、その人自身の気持ちにも、そっと目を向けてみてください - 周囲の人へ
人はそれぞれ、違った背景や想いをもとに、自分なりの選択を重ねています。
「こうあるべき」と決めつけるのではなく、多様な選び方を認め合える空気を、私たちの言葉や態度で少しずつ育んでいきましょう。