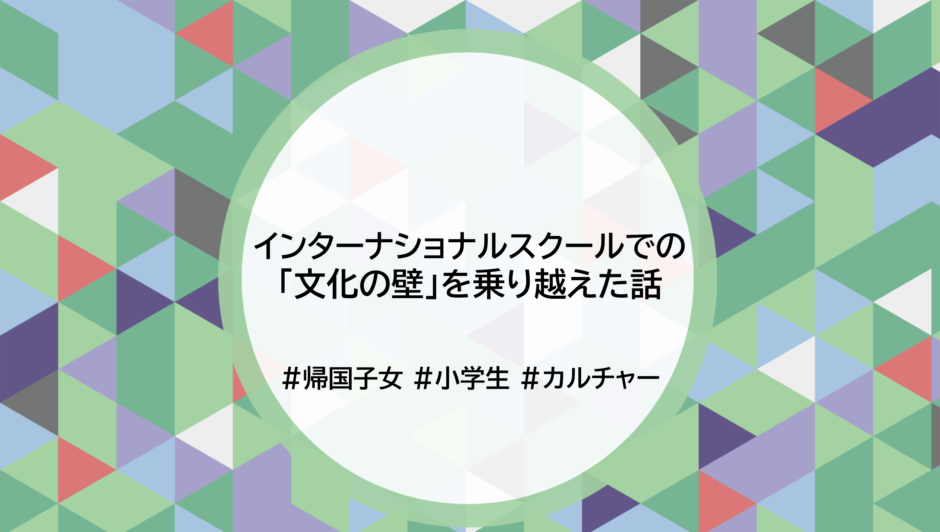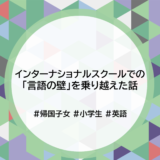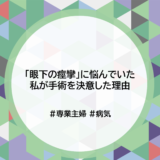今回は、小さい頃に海外で暮らしていたハリーさんに、「当時困っていたこと」や「今みんなに伝えたいこと」を聞いてきました!
【背景】小さい頃の体験談

子どもの頃はどのように暮らしていましたか?

生まれてから小学校4年生まで、オーストラリア・上海・香港で暮らしていました。

小学校4年生のとき、どうして日本に帰ることになりましたか?

日本の中学校を受験することになったからです。お父さんは単身赴任で、お母さんとお兄さんの3人で暮らしていました。

日本に帰ることが決まったとき、正直どのような気持ちでしたか?

「友だちできるかな」という不安はありました。すでに仲良くなっている状態の集団に飛び込むのは、かなり不安でした。また、インターナショナルスクールでもようやく友だちができた上、勉強もわかるようになってきたタイミングだったので、残念でした。

また、「日本語で話せる嬉しさ」より、「先生に怒られないか」「一人ぼっちにならないか」「勉強についていけるか」という不安の方が大きかったです。通い始めてからも、日本の文化に慣れるまでは大変でした。

帰国後、海外と日本に差は感じましたか?

「こんなに違うの!?」と、大きなカルチャーショックを受けました。

まず、学校に水筒やお菓子を持っていけないことが衝撃でした。 そして、児童全員がランドセルを使う文化にも驚きました。

私はランドセルを持っておらず、リュックで小学校に行きました。しかし、行ってみたら周りはみんなランドセルで、「みんなランドセルだからランドセルで来なさい」と、先生に注意された記憶すらあります。

教科書を持っていけばいいだけなのに、ランドセル文化が当たり前なのは私も不思議だと思います。

他の驚きでいうと、教室の人数も全然違うことがあります。海外では1クラス20人弱ですが、日本では40人ほどいたからです。

しかも、私が通っていた海外の学校では、20人の生徒に対して先生が2人ついていました。これも日本と海外で全然違いますね。

特に香港では、アジア人などの英語が堪能ではない人のための英語クラスがあって、先生1人に対し生徒が4〜5人の授業をしてくれました。この形態は、日本の支援級に近いと思います。

でも、英語が堪能な他の生徒は、少人数クラスで教えてもらえることを羨ましがっていて、この温度感は「日本の支援級との違い」ですね。

また、振り返ると海外では、発達障害や精神障害を抱える人も、みんなと同じ教室で授業を受けていました。だからこそ、日本に来てからも障害者手帳のある人と接する上で、境界のようなものは感じませんでした。全員1人1人違うから、「この人はこういう人なんだ」と考えていました。

私自身、海外にいたときは「自分はアジア人で英語があまり得意でない人」でしたが、周囲から差別されることは特にありませんでした。そういう一人一人の違いに関係なく、みんながお互いに認め合って、一緒にスポーツなどをしていました。

多様性が認められているクラスだったのですね。

すごく認められていましたね。

一方で、日本に来たら全員同じことをするのが普通という雰囲気だったのが、カルチャーショックでした。

今思うと、先生1人に対する生徒人数が多いため、そう(全員が同じことを)しないと回らないという、仕組み面の問題かもしれません。

日本では人材不足により、少数の先生が大人数の生徒をみるため、学校では規律を守る必要があるのかもしれませんね。

そうですね。 その上で、日本では「支援級」と呼ばれるしくみがありますね。特に配慮が必要な人たちが、ホームルーム以外の授業は、別の教室で支援を受けられるような形式です。
【困りごと】当時、困っていたこと

日本に帰ってきてから、困ったこと・つらかったことを具体的に教えてください。

帰国子女であることに対し、いじめではないけれど、嫌味のようなことを言われました。友だちも多かったけれど、そのときに言われたことは今でも覚えています。

自分で気づいていないだけで、傷になっているかもしれませんね。

そういう傷が重なって、「目立たないようにしよう」「でしゃばらないようにしよう」と、当時考えたこともあります。

教育制度や周囲に対して、当時寄り添って欲しかったことはありますか?

国語の中でも、読み上げが特に苦手で。あまりに内容がわからないと眠くなってしまうので、授業から置いていかれることもありました。

これは生徒側にも原因があります。一度苦手意識を持つと、授業も眠くなるし、面白くなくなってしまいます。 だからこそ、可能ならば、苦手科目でさえも眠くならないような、興味がもてる授業だと、生徒としては嬉しいですね。 エンターテインメント要素は、本来先生に求めるものではない気もしますが、非常に重要な要素だと思います。

誰しも苦手な授業はあると思います。勉強全般が苦手な子は、すべての授業に対して、その感覚を持っているのかもしれませんね。

友だちにして欲しかった配慮はありますか?

クラスで浮いてしまったときや孤独感を感じているときに、受け入れてくれる友だちがいるだけですごく嬉しいと思います。実際に私はかなり助けられました。

世の中、カルチャーの違いを感じて浮いたり叩かれたりする帰国子女もいるので、周りと違うことを受け入れてほしいです。

「受け入れる」というのは、具体的に何をすればいいのでしょう。実際の体験をもとに、具体的に教えてください。

鬼ごっこに混ぜてもらえたことが仲良くなったきっかけです。要するに、浮いていても仲間はずれにせず、誘ってくれることですね。

声をかけられたことで「自分はここにいていいんだ」「今日も学校に行こう」と思え、自分の存在を認めてくれていると感じました。だから、声かけはすごく嬉しかったです。
【合理的配慮】いま、声をかけるなら

ハリーさんなら、帰国子女の人に何と声をかけますか?

「鬼ごっこしようぜ」と言います。

上手く声をかけられなくても、休み時間に近くの席で一緒に話したり、折り紙をしたり、時間を共有できる人がいるだけでも心強いと思います。

もう一度、昔の自分になったとしたら、どのような行動を起こしますか?

スポーツを通して友だちを作りますね。友だちを作るきっかけは重要だと思っていて、スポーツはすごい良いきっかけになると思うんです。

一緒にやるだけで、話さずとも交流ができて、仲良くなれたという感覚になるからです。

だから自分だったら、休み時間の遊びや体育の授業を通して、全力投球で楽しくスポーツします。

それから、周りの同級生をよく観察して、この人と話したいなと思う人に話しかけに行きます。

やはり、自分から話しかけたり興味を示したりすることも、大事だと思います。

受け身の姿勢ではなく、自分から動くことも大事ということですね。

話さないことには始まりません。話しかけるのが難しかったら、スポーツを通して仲良くなっていくといいと思います。

言葉でのコミュニケーションが難しければ、言葉を使わないコミュニケーションを取ればいいということです。

ご家族の立場だったとしたら、何をしますか? 親は学校にいられないので、フォローも難しいのではないでしょうか。

まず、圧倒的味方でいることを大切にします。どんなときでも「親である自分は裏切らないよ」というスタンスが必要だと思います。

学校で孤立していた場合、親が敵になると家でも孤立します。そうして居場所がなくなると、どんどん悪化する一方です。

例えば、家に帰ってきたら、時間を作って学校での話をたくさん聞いてあげます。

お子さんがどうしても環境に馴染めないときは、家以外の別の居場所を作ってあげることも良いと思います。 例としては習いごと・ボランティアなどのコミュニティが挙げられますね。

家族が直接できることもあれば、間接的にできることもあるんですね。

そうですね、アドバイスをするのではなく、ひたすら話を聞いてあげることが重要かもしれません。自分の中でもつらくてしんどくて混乱しているときは、人の言葉が届きづらくて、アドバイスは時に責められているように捉えてしまいますから。

だから、聞いて受け入れることです。そこに評価は入れません。事実ベースで受け入れてあげる、そんな風に傾聴すると良いと思います。

ありのままを受け止めてあげる役割が、周りの大人に求められていることなのかもしれないですね。

最後に、読者の皆さんに一言お願いします。

今いる居場所だけがすべてではないということを忘れないでほしいですね。 万が一、環境や人との相性が合わなくとも、自分に合う場所を探しに行けばいいんです。

あまり孤独にならず、追い込まず、人生を楽しんでいただけたらと思います。

苦しむために生きているのではなく、楽しむために・幸せになるために生きています。

そういうメッセージを帰国子女で悩んでいる人に届けたいです。
- 同じ境遇の人へ
人生は楽しむためにある、今の場所が全てではない、決して孤独ではないことを知っていてほしいです。 - 身近な人(家族・親友・恋人)へ
言葉の有無に関わらず、コミュニケーションを取り続けてください。 - 周囲の人へ
できる限り、ありのままを受け入れて、傾聴してください。それだけで「居場所」になります。